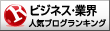【2022年8月 告知】これまでご覧いただきありがとうございます。
いろいろと小生も動きがありました。波乱や混乱、そして更なる高みへ(笑)
メールでもいろいろとご心配や励ましのお言葉をいただき、感謝です。
今後はNOTEなどで詳細やこれからの放デイ、そしてこれからの小生の展開を述べさせていただきます。また開設したら報告いたします。
なにかあればまたメールください。pvdyv34761@yahoo.co.jp

【ご必読ください】児童発達管理責任者および管理者、そして指導員の方たちへ
施設を利用するこどもたちの将来を見届けることはほとんどありません。
しかしこどもたちの将来の可能性(幅)を広げることの一助を担うことはかないます。
そんなところまで見れません、という方は当ブログを読まないでください。
大変なのはわかった上での知識、いや意識ですから。
今回は職員・スタッフには見ておいてほしいモノを列記しました。
無料で資料の請求ができますので、ぜひご参考にどうぞ。
カリキュラムにパソコン導入を検討中。対人に不得意でもパソコンは無限の可能性。
自宅にいながら本格的プログラミング学習|Tech Kids Online Coaching ![]()
Z会プログラミング講座 with LEGO(R) Education/資料請求はこちら ![]()
小学校~高校編
こんなお仕事選びがあるということを教えてあげてください。
高校生必見!好きなことを学びながら大卒資格が取れる専門の学校 ![]()
わが子のやる気を引き出す伝え方・励まし方がわかる!伝え方コミュニケーション検定 ![]()
★クラフト感覚でできる人気の在宅ワーク技能!>>> 建築模型製作講座 ![]()
親御さんにサイトを紹介すれば本当に気が楽になると思います。
いかがでしょうか?
一度請求して見ておくと利用者のご家族との話は盛り上がります。
あくまでサポートですのででしゃばらないよう気を付けてください。
当ブログに関してのご質疑は サラリーマンK 迄 : pvdyv34761@yahoo.co.jp
クリック応援お願いします。